令和6年度エコパートナー環境学習等業務委託で行われた事業について
問い合わせ番号:17442-5082-1166 更新日:2025年 4月 17日
本市に登録しているエコパートナーに対して実施している、エコパートナー環境学習等業務委託事業の活動報告です。ぜひご一読いただき、皆さまの環境活動の一助としていただければ幸いです。
令和6年度 エコパートナー環境学習等業務委託
活動テーマ 自然環境保全
1.吉崎海岸自然共生サイト調査事業業務
報告書サムネイル
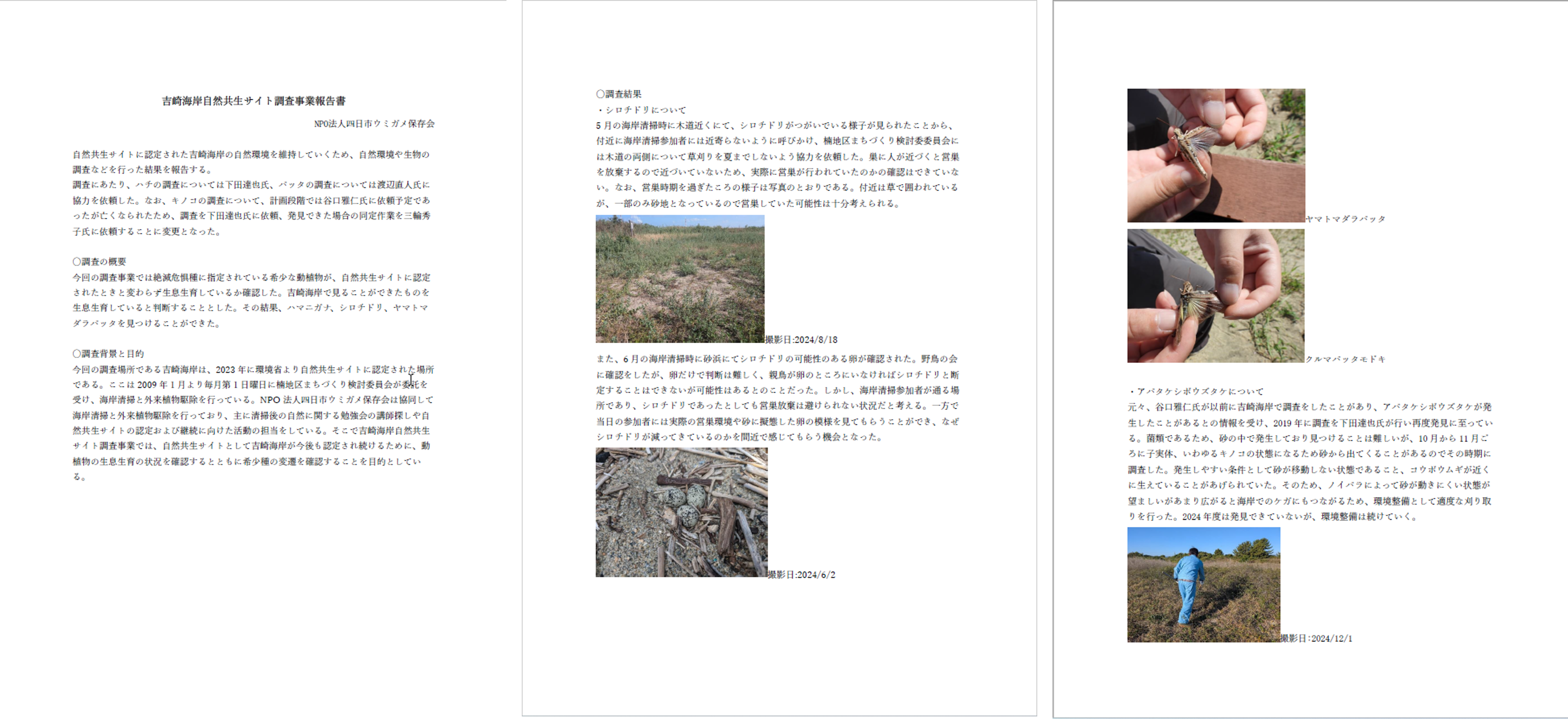
概要
◆事業の目的
市内の貴重な砂浜海岸であり、令和5年に環境省により自然共生サイトに登録された吉崎海岸の豊かな自然環境を維持していくために希少な動植物等の調査・観察を行う。
また、調査・観察で得た結果をもとに掲示物を制作し、主に吉崎海岸に訪れる人を対象とした生物多様性及び吉崎海岸という場の価値について啓発を行う。
◆実施内容
(1)希少な動植物等の調査・観察
・動植物それぞれの調査・観察に適した時期に現地で調査・観察を行い、また、必要に応じて専
門家を招いての調査を行う。
(2)啓発
・調査・観察で得た結果をもとに、掲示物を制作し、吉崎海岸にて掲示を行い生物多様性及び吉
崎海岸という場の価値について啓発を図る。
◆事業の結果、考察
調査の結果、ハマニガナ、シロチドリ、ヤマトマダラバッタなどの希少動植物の生息が確認できた。毎月の海岸清掃とともに、外来植物の駆除を実施していることがハマニガナの生息分布につながっていると実感できた。
活動テーマ 竹林整備 持続可能性
2.竹林整備を継続するための幼竹加工食品(四日市産メンマ)づくりの調査・研究業務
報告書サムネイル

▶詳細はこちら(報告書)(PDF/1222KB) 添付書類(1)(PDF/95KB) 添付書類(2)(PDF/733KB) 添付書類(3)(PDF/264KB) 添付書類(4)(PDF/136KB)
概要
◆事業の目的
昨今、竹林の里山整備を持続的に行っていくために、新たな竹の活用法を見出すことが求められている。四日市市内においても、竹林の里山を持続的に制御するため、幼竹をメンマなどの加工食品として活用する可能性を探るための調査・研究を行う。
◆実施内容
(1)幼竹を用いたメンマづくり及び研究の実施
・ハチク、マダケの幼竹の塩漬けづくり、レトルトパウチ化を行い、食品としての有用性を探る。
・レトルト化した幼竹を用いたレシピの開発を行う。
・竹の種類によるメンマの利用方法の研究を行う。
(2)先進事例視察、情報収集
・富山県上市町、三重県桑名市などの先進事例を視察し、情報収集を行う。
・純国産メンマプロジェクト全国大会に参加し、情報収集を行う。
・市内タケノコ生産者の竹林整備方法の聞き取りを行う。
◆事業の結果、考察
(1). 幼竹を活用した竹菜作りは、放置竹林対策として自立的に成り立つ有効な方法であることがわかった。
(2). 全国の動きをみると放置竹林対策には、竹活用の事業化が必要であり、進んでいる地域では、企業の参加がキーになっており、それに対する行政の支援もある。
活動テーマ ごみ削減 市民協働
3.集合住宅向けベランダ型キエーロに関する調査・研究業務
報告書サムネイル

概要
◆事業の目的
四日市市では、ごみの削減に取り組んでおり、家庭から排出される生ごみを削減するために、家庭への循環型生ごみ処理機「キエーロ」の導入を促進している。しかし、従来型の「土置き型キエーロ」は底板がなく直接地面に設置する構造であるため、地面のない集合住宅等での設置に不向きである。集合住宅等での設置も可能なベランダでの設置を想定した「ベランダ型キエーロ」の仕様及び啓発指導方法について調査研究を行う。
◆実施内容
(1)ベランダ型キエーロの仕様の開発
・底板を有し、キエーロ内の土が処理器の外部と分離される構造、家庭で排出される生ごみが十分に分解される運用が可能であるキエーロの開発
(2)ベランダ型キエーロの運用及び啓発方法の調査研究
・ベランダ型キエーロは、土置き型キエーロとは設置場所の周辺環境及びサイズ感が異なり、異なる運用や啓発方法が必要となるため効果的な方法についての研究
・ベランダ型キエーロの普及が進んでいる神奈川県鎌倉市での取り組みについての調査
◆事業の結果、考察
ベランダの広さや環境以外にも、マンション特有の間取りや通路の幅、掃き出し窓からの動線などを考慮すると大きな処理機を運び込むのはむずかしいケースが多いと考えられる。
排出される生ごみ量と1 台の処理機のサイズを合わせるだけの発想では普及は進められないことが分かった。例えば、耐荷重性を考慮し、小型の処理機を複数分散して設置し、微生物分解に必要な基材の容量を確保する・バッグ式などと併用するなども解決策になると考えられる。
啓発内容に関しては、一筋縄ではいかないことが明確であるから、鎌倉市の3Rの推進などを参考に、四日市市でも市民・事業者・行政が一体となって廃棄物の抑制に取り組み、ごみ減量の意識の底上げを行うことが重要である。
活動テーマ SDGs 市民協働
4.「ともに学び・行動!SDGsを市民の手で」SDGsを自分事として考える講座等運営業務
報告書サムネイル

概要
◆事業の目的
持続可能な開発目標(SDGs)の達成のためには、地域の団体や市民一人ひとりが「自分ごと」としてSDGsを考え、日々の生活活動を改善していくことが重要である。本業務では、SDGsの中でも環境に特化した内容で、一般向け、親子向けに講座を実施し、講座で学びを得た参加者に対し「SDGs宣言」を行っていただく。
◆実施内容
(1)講座の実施
・一般市民・市民活動団体向けの講座を5回、子ども・親子向けの講座を3回(うち1回は共通)実施する。
・講座は参加者が楽しく学ぶことができるようワークショップや見学会を行うなどして工夫する。
(2)「SDGs宣言」の実施
・講座参加者に「SDGs宣言」を行っていただく。
・「SDGs宣言」はホームページやメディア等で広く周知を行う。
◆事業の結果、考察
・「講座内容がよかった」とアンケート等からの感想が多くあり、充実したプログラムを実施できたと実感する。
・各方面での公募を行った結果、多くの参加者を集めることができた。また、併せてSNSも活用することができた。
・講座内容に連続性を持たせることで、SDGsの基礎知識をワークショップや体験を通じて参加者に伝えることができた。
・最終的に参加者にSDGs宣言を行っていただき、市民のこれからの行動変容につなげることができた。
・一方で、若年層の参加が少なかったことが課題であるため、若者への働きかけも重要であると考える。
○今後同様の講座を実施する際には、若い世代や学生の参加を促したい。学び続けることも重要であり、継続する場合にはSDGsの多彩な目標を取りあげるなど深化を図り講座の価値を高めたい。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412



